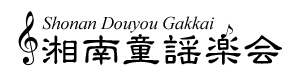「歌こそ音楽」となかにし礼さん
◆湘南童謡楽会の毎月の配布資料(月報)に、今年初めから「音楽の木漏れ日」または「音楽の木陰」と題した“音楽こぼれ話”を書いています。14年7月号に書いたものをみなさんに読んでいただきます。夏場なので、「音楽の木陰」のタイトルになります。なかにし礼さんの、歌にかかわる一文です。以下に月報のままを掲げます。
◆『天上の音楽 大地の歌』(音楽之友社)は、作詞家・作家のなかにし礼さんの名著(図書館から借りたらすりきれるほど読まれていて名著の証しか)と言えるでしょう。その中の「歌こそ音楽」の一章に、大いに共感しました。次が全文です。
一五〇〇年以前は、実際上、音楽といえば、それは声楽のことであった。十六世紀になっても音楽の九割が声楽であった。バロック時代になってやっと、声楽と器楽の量がほとんど同じになり、一七五〇年以降になって初めて器楽の方が優勢になったのである。
で、われわれ日本人が西洋音楽の影響を受けるようになったのが百十年前、すなわち、西洋音楽においても器楽が全盛を誇っていたころなのである。だから、日本人は音楽と言えば、器楽音楽のことを頭に浮かべ、声楽のことをないがしろにするような習性がいつの間にかできてしまった。
実はこれは日本人にとって大いに不幸なことであった。音楽とは、本来<歌>であり、その<歌>のメロディそのものは、各民族の音感にそって生まれるものだということをその時点で知っていたら、日本古来の歌や音楽を否定して、西洋音楽に右にならえするような真似はしなかったはずなのである。
すでに述べたことだが、メロディとは、メロス(旋律を意味するギリシャ語)と、オード(ギリシャ劇で合唱隊のうたう詩)という二つの言葉が合体して出来たものであるなら、メロディの母は言葉以外の何ものでもないのだ。なのに日本人は耳ざわりの良さをいいことにして西洋の器楽音楽をせっせと吸収することに精を出し、音楽とは一体何なのかを深く考えることを避けてきたふしがある。声楽には言葉があり、その言葉が障害をつくり、壁をつくり、理解されることを拒絶する。そこでますます器楽を愛した。が、どっこい器楽には言葉がないと思ったのはとんでもない考え違いで、器楽といえども、その旋律の母は言葉なのである。
バッハやベートーヴェン、ブラームスの音楽の土台にはドイツ語があり、ドビュッシーやラベルの音楽を綾なしているのはフランス語であり、ロッシーニやヴェルディの器楽音楽とともに歌っているのはイタリア語である。そう思うと彼らの音楽まで遠のいていく。それがイヤだから、純粋音楽だけを楽しもうとする。要するに器楽音楽の上澄みだけを聴いて、「音楽に国境はない」などとうそぶいているのである。
声楽となるともっとひどい。そこで意味のある言葉を歌っているにもかかわらず、その意味さえ素通りして、声の良さだけを堪能しようとする。声の良さなどというものは音楽でもなんでもないのだが・・・。
そこでわれわれ日本人は、西洋音楽の<歌>をもっともっと聴いたほうがいい。知ろうとすればするほど理解不可能なものの前でのたうちまわったほうがいい。そうすれば、日本の音楽のあるべき姿がおぼろにも見えてくるのではないだろうか。
器楽音楽は今や、無調となり、旋律さえ必要としない時代になってきている。が、この世界に民族の魂である言葉があるかぎり、旋律は生きつづけ、<歌>は生まれつづけるのである。
歌は音楽の始発駅であり、終着駅でもあるのだ。